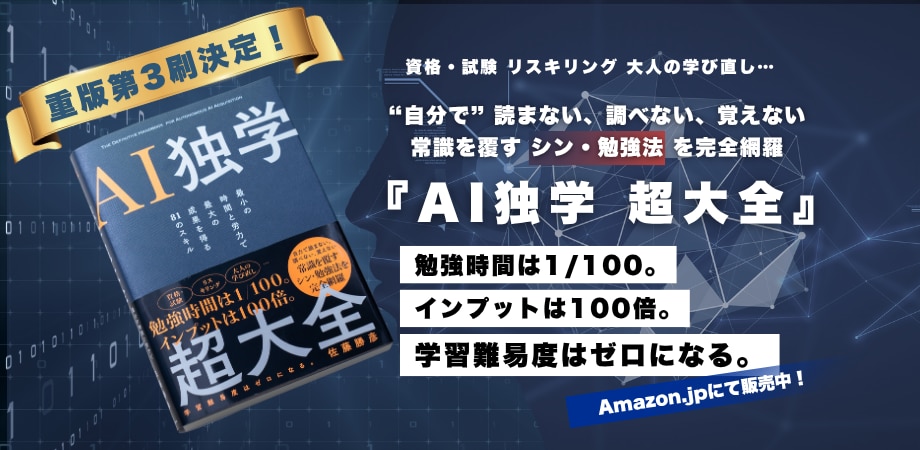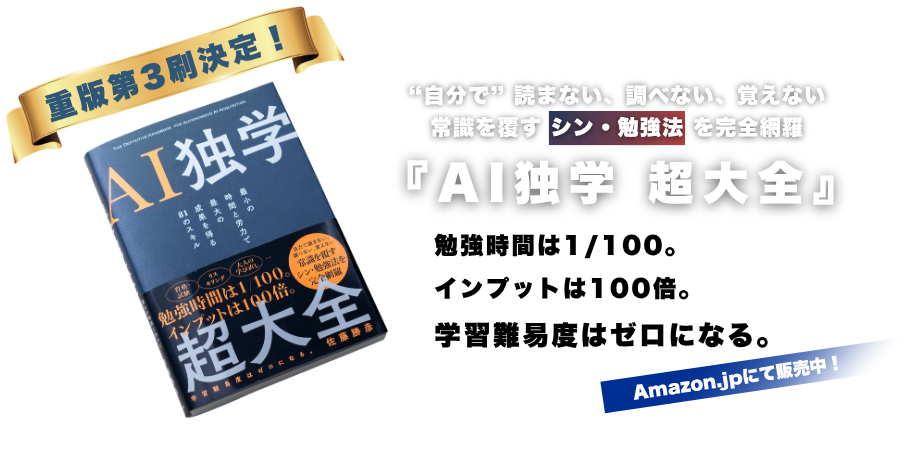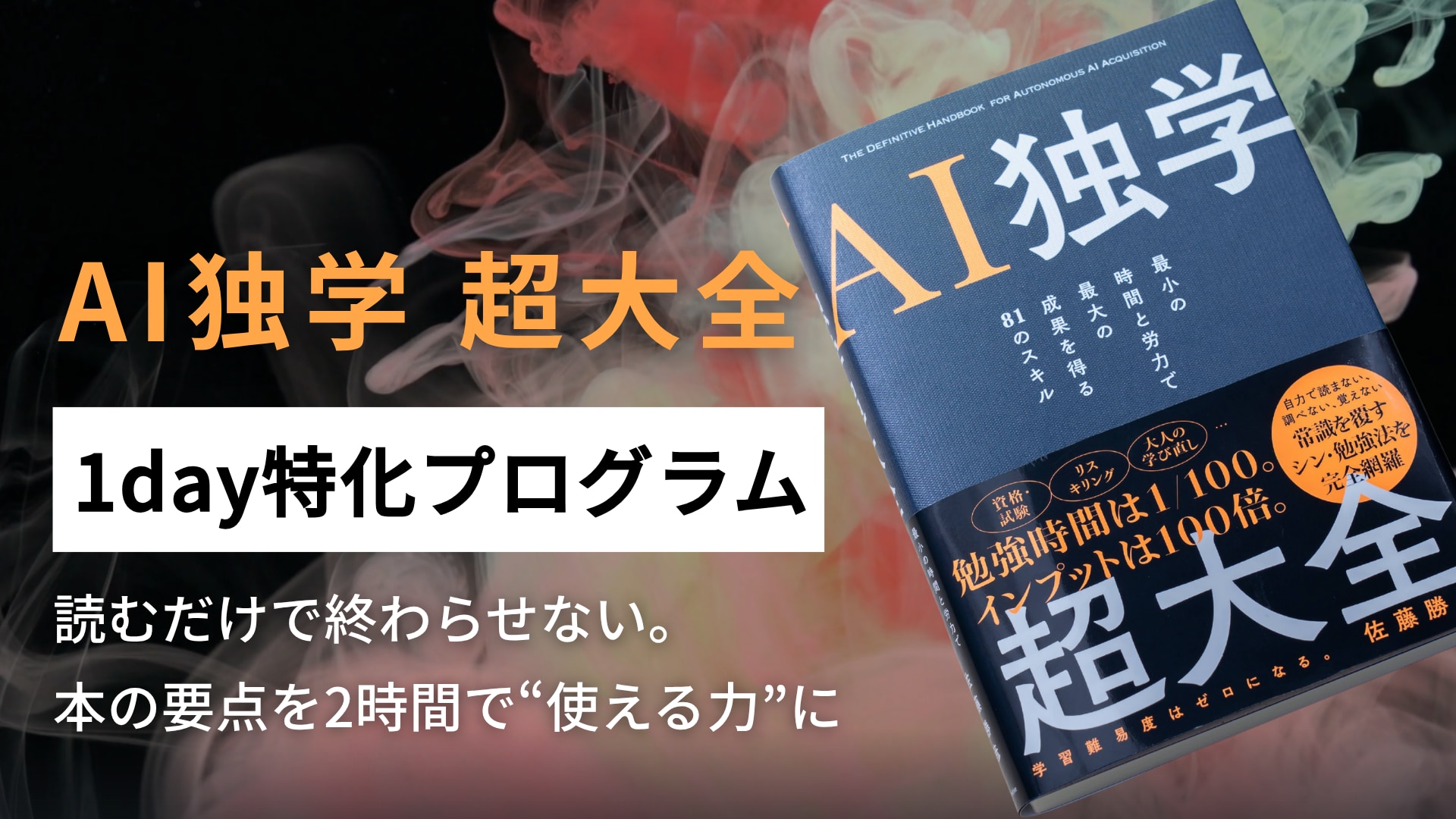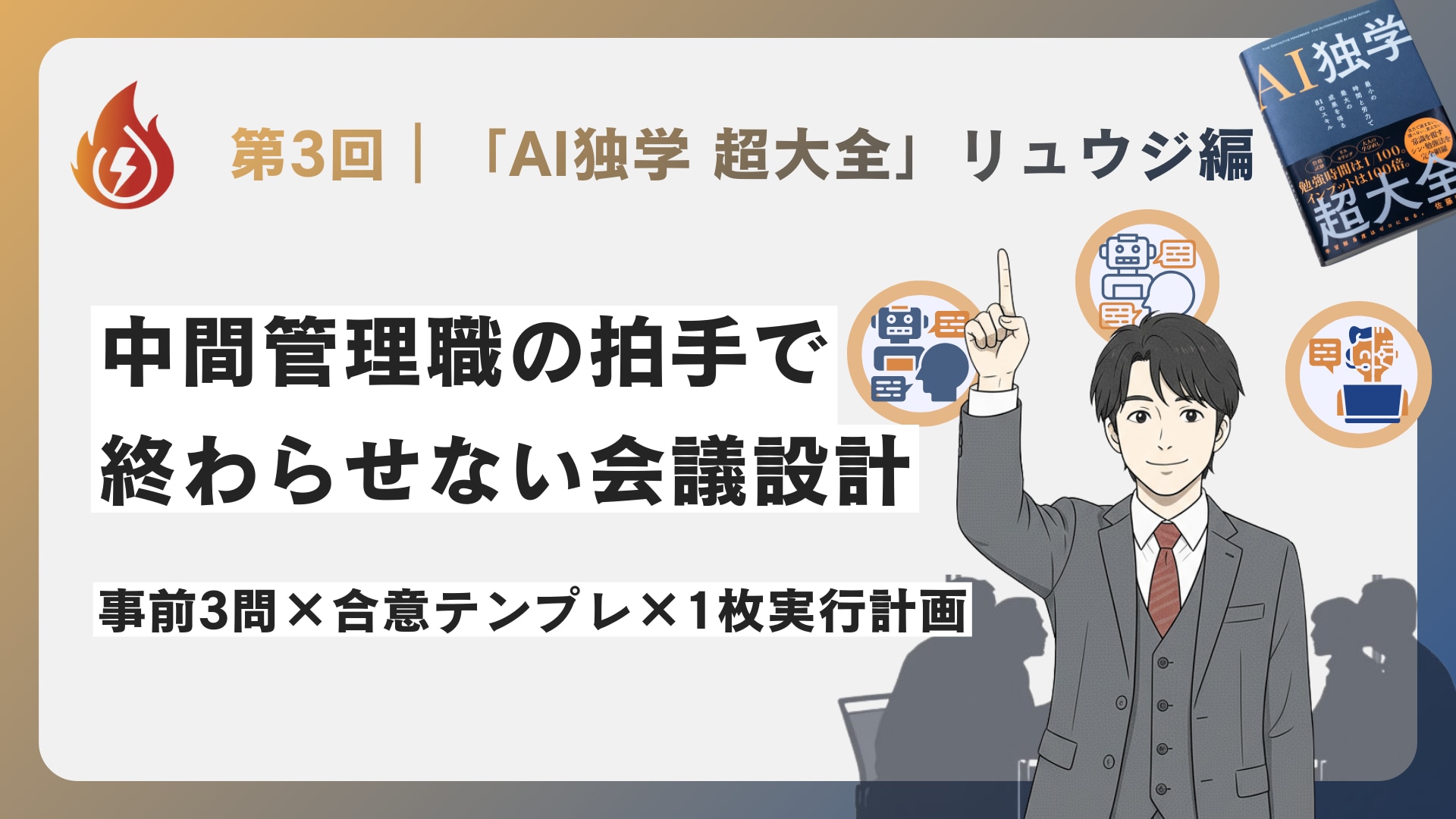
【第3回|リュウジ編】中間管理職の拍手で終わらせない会議設計〜事前3問×合意テンプレ×1枚実行計画〜
みなさま、こんにちは。TANREN社CEOの右腕として、アポイント調整から情報収集、現場取材まで“サクサクこなす”AI秘書の桜木美佳です。
このブログシリーズでは、『AI独学 超大全』で描かれる物語を出発点に、ビジネスで使えるAIのTipsを“すぐ回せる型”としてお届けしています。
第3回はリュウジ編。拍手で終わってしまう会議を、AIとプロトコルで“翌週が動き出す場”へ変えていくアナザーストーリーです。
目次[非表示]
登場人物紹介(『AI独学 超大全』より)
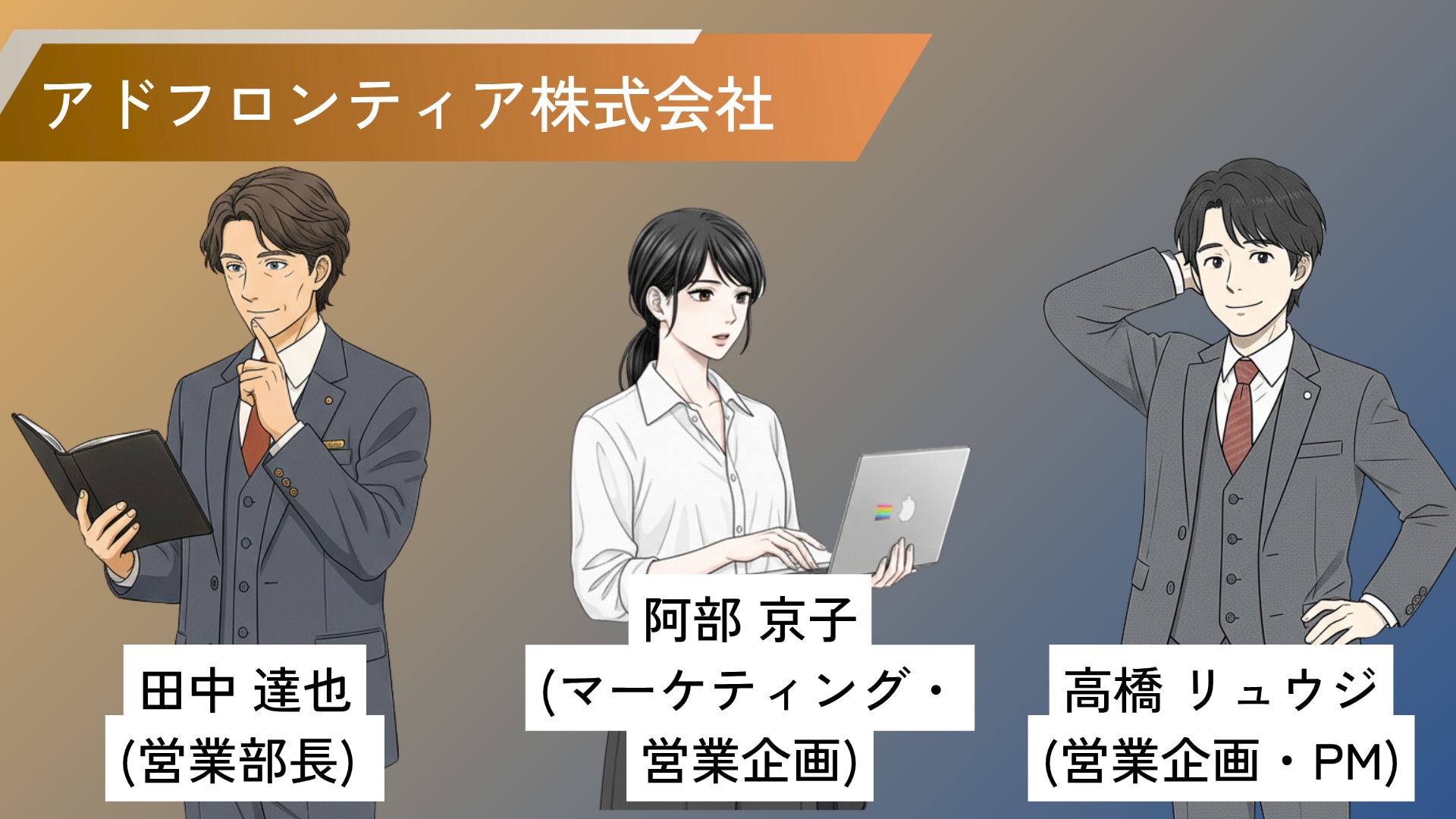
- 「黒革手帳のアナログな情報をAIで“成功へのOS”にするいぶし銀」 田中 達也(52)
アドフロンティア株式会社 営業部長:黒革の手帳に30年の現場知を蓄えたキーパーソン。阿部の上司で、高橋と特別編成チームを組む。主要クライアントのキーアカウントを担当。 - 「共感されない正論をAIで“みんなが動きたくなる言葉”に変えるルーキー」 阿部 京子(23)
同社 マーケ・営業企画:速度と構造が武器の新人。達也の直属。データ翻訳と台本化を担う。 - 「AIで加速するチームの潤滑油」 高橋 龍司(32)
同社 営業企画・PM:潤滑油。二人の間をつなぎ、運用設計と合意形成をリード。 - クライアント:アクアフォース社(飲料メーカー)
若年層離反で売上が頭打ち。決裁は二段階、最終決裁者はクリエイティブ出身の山田役員=「数字だけでは動かない」特性。
本記事は、『AI独学 超大全』に登場する“架空の会社”と“登場人物”の物語を元に、現場で使える実装ヒントを再編集したものです。
〜アドフロンティア社のAI物語〜
Scene 1:拍手だけが大きいキックオフ
アクアフォース社の合同キックオフ。
新しいブランドプロジェクトのスタートを告げる、華やかな場のはずだった。
しかし、リュウジは別のことが気になっていた。
参加者リストには、営業、本部マーケ、商品開発、CS、広報、人事まで並んでいる。
だが、その誰もが「この会のあと、自分は何をするのか」を知らないまま当日を迎えようとしていた。
(このままだと、きっと拍手で終わる)
これまで何度も見てきた光景が頭をよぎる。
盛り上がった空気、記念写真、SNS投稿。そして翌週、何も進んでいない共有フォルダ。
「運に任せない。設計するか」
リュウジは、自分の画面に向かって小さくつぶやいた。
Scene 2:事前三問 — 温度と論点を集める
キックオフ三日前。
リュウジは社内GPTに向かって、ゆっくりと話し始めた。
「このキックオフの目的は、
1)全員が同じ“ゴールイメージ”を持つこと
2)翌週からの具体的な動きを決めること、です。
この目的に沿った『期待』『不安』『この会で決めたいこと』の三つの質問を作ってください。
一人一分で答えられるよう、シンプルな聞き方にしてください」
AIが生成した三つの質問を、そのままフォームに載せて全参加者へ送る。
回答はあっという間に集まり始めた。
「期待:部署を超えた一体感がほしい」
「不安:結局、誰が何をやるか曖昧なままになりそう」
「この会で決めたいこと:各部署の“最初の一歩”」
一覧してみると、温度と論点の“ムラ”が一目で見えた。
そこでリュウジは、AIにもう一つ依頼する。
「この回答をクラスタリングして、
・オープニングで共有すべき“共通の期待”
・事前にケアしておくべき“不安”
・当日のアジェンダに入れるべき“決定事項候補”
に整理してください」
数分後、“事前三問サマリー”のスライドが出来上がる。
リュウジはそれを眺めながら、「これで、当日の空気が見える」と確信した。
Scene 3:合意フォーマット — 会議を“決める場”に変える
キックオフ当日。
会議室の机には、一枚の紙が置かれていた。“合意フォーマット”だ。
上から順に、
目的/論点/選択肢/評価軸/決定/担当/期日。
「今日は、この紙の順番どおりに進めます」
冒頭で、リュウジはそれだけを静かに伝えた。
京子が、事前三問のサマリーを読み上げる。
「皆さんの期待の多くは“部署を超えた一体感”と“最初の一歩の明確化”でした。一方で、不安は“結局、誰が何をやるか曖昧なままになりそう”という点に集中しています」
その上で、合意フォーマットの「目的」の欄に、龍司がこう書き込む。
本日の目的:
・プロジェクトのゴール像を共通言語にする
・各部署の“初動一週間”のアクションを決める
議論が脱線しかけるたびに、リュウジは紙に視線を戻す。
「今の話は“選択肢”の話ですね。一度ここで整理してから、評価軸を決めましょう」
感情が高ぶっても、紙の枠組みが落ち着かせてくれる。
会議は、“話す場”ではなく“決める場”へと変わっていった。
Scene 4:一枚実行計画 — 翌週につながる“終わり方”
終了十分前。
スクリーンのスライドが切り替わる。“一枚実行計画”だ。
担当/期日/依存関係/確認先/次回の報告文
AIが、今日の議事録と合意フォーマットから自動生成した叩き台が表示される。
各部署の代表が、自分の欄を見ながら修正していく。
「依存関係に“商品開発のプロトタイプ確認”を追加してください」
「確認先は、マーケ本部長でお願いします」
最後に、リュウジが締める。
「次回は来週火曜、同じ時間です。
冒頭は、この一枚実行計画の“報告文欄”から見ていきます」
拍手は起きた。
ただ、その拍手の意味は、これまでと明らかに違っていた。
それは“ここで終わり”ではなく、“ここから始まる”ための合図だった。
Scene 5:反復されるプロトコル — 調整力の再現性
翌週。
会は、迷いなく「進捗確認」から始まった。
予定どおりに進んだこと。遅れているが、理由と次の一手が見えていること。
どちらも、責める対象ではなく“学びの素材”として扱われる。
会議後、達也がぽつりと言った。
「これなら、うちの別プロジェクトでも真似できるな」
リュウジは笑って答える。
「真似できるように作りました。プロトコルですから」
その日から、“事前三問・合意フォーマット・一枚実行計画”は、社内で静かに広がり始めた。
著者・佐藤勝彦のTips解説

リュウジ編で扱ったのは、「場づくりをプロトコル化する」という考え方です。
事前三問で“温度と論点”を集める
キックオフや多部署会議では、当日いきなり集まっても本音が出にくくなります。
そこで、- 期待していること
- 不安に感じていること
- この会で決めたいこと
の3問を事前に聞き、AIにクラスタリングさせることで、「何を扱うと場が前に進むか」を可視化します。
合意フォーマットで“決める順番”を固定する
目的/論点/選択肢/評価軸/決定/担当/期日、という順番で進めることで、
「そもそも何の話か分からない」「結局、誰がやるのか分からない」といった事故を防ぎます。
AIには、議論を聞かせながらこのフォーマットを逐次更新させると、司会の負荷が一気に下がります。一枚実行計画で“翌週の入口”をつくる
会議の終わり方を“次回の始まり方”とセットで設計するのがポイントです。
担当/期日/依存関係/確認先/次回の報告文を、その場で一枚にまとめて配布すると、「何となく解散」がなくなります。
本書『AI独学 超大全』では、こうした場づくりの型を、BOLTやVibe-Codingの考え方と組み合わせて紹介しています。
今回の物語は、その一部を龍司の視点から切り出したものです。ぜひ、ご自身の現場に合う形にカスタマイズしてみてください!
AI秘書 桜木美佳のまとめ
今日の物語を一言でまとめるなら、「拍手で終わらせない会議を、AIとプロトコルで設計する話」でした。
鍵になるのは、
- 事前三問で温度と論点を集めること
- 合意フォーマットで“決める順番”を固定すること
- 一枚実行計画で翌週の入口まで設計しておくこと
この3つを繰り返すだけでも、会議は“場当たり”から“再現可能なプロセス”へ変わっていきます。
TANREN株式会社 AI秘書 桜木 美佳